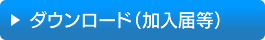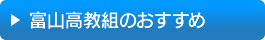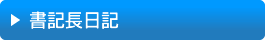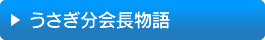ようやくに雨があがる。さて、週始めの9日・月曜日の昼に書記局前のいたち川でボケていたら、祭りの太鼓が聞こえた。「ムムム…」と大道に出ると、千歳神社の一行に出会った。
ようやくに雨があがる。さて、週始めの9日・月曜日の昼に書記局前のいたち川でボケていたら、祭りの太鼓が聞こえた。「ムムム…」と大道に出ると、千歳神社の一行に出会った。
千歳神社とは、書記局のすぐそばにある神社(左写真)。「日の丸」が仰々しいが、この日が祭礼日なのだ。この社の由緒は以下の通り。
千歳神社由緒
当社は天照大神、豊受大神を祭神とし、富山の土地神として最も古い神明社であり、相殿には誉田別之命を祀っています。
天正九年(1581)佐々成政公が、越中五十四万石を領して富山城主となった時、敬神の念が厚かったので、この神明社を産土大神として崇め、 城下町富山を東西に二分し、東は北の神明、西は南の神明と称し、それぞれ富山の守護神としました。 当神社は北の神明にあたり、当時は蛯町の地に鎮座していましたが、富山藩祖前田利次公が入場後、 寛文年間城下の町割りに際し現在地に移られました。
相殿は文化七年(1810)九代藩主前田利幹公が、東田地方(今の城北町)に八幡神社を創立し、鬼門除けの宮と称していましたが、 明治四十五年(1912)当社に相殿として合祀し、その際神徳の弥栄を寿いで、神明社を千歳神社と改称されたのであります。
千歳の称号は、十代藩主前田利保公が、嘉永二年(1849)東出丸(今の桜木町)に、 隠居所として千歳御殿を造りこれより神通川の下流奥田あたりまでを、千歳側と名付け、桜を植えて千歳桜と呼び、 富山の名所として事に因んで称せられたものであります。
往時境内には欅を初め藤等、大樹老木鬱蒼と繁り、森厳清浄な神域を保ち、由緒深い神社であることを想わしめ、 近くには岩瀬に通う舟着場等もあり、富山東北の繁華街関門として賑わっていましたが、 昭和二十年八月戦災によって社殿は勿論附近悉く焼失致しました。 現在の本殿及び拝殿は昭和三十一年氏子有志によって再建されたものであります。
 祭礼の一行の衣装は、かなり本格的(左写真)。太鼓に加えて、笛や笙の音も聞こえる。さすがに古い社である。
祭礼の一行の衣装は、かなり本格的(左写真)。太鼓に加えて、笛や笙の音も聞こえる。さすがに古い社である。
春は祭りを呼び、祭りが華やいだ春の雰囲気を高める。我が上市町の最大の祭りは「市姫神社」の春祭(6月)で、やや先であるが、何とも待ち遠しい想いがした。