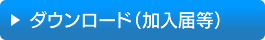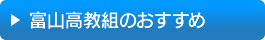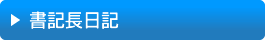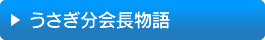このお盆の間に友人から贈られた書物を1冊読んだ。書名は『私釈法然』。著者の伊藤益(すすむ)氏は親鸞研究者。私の大学時代からの親友だ。
このお盆の間に友人から贈られた書物を1冊読んだ。書名は『私釈法然』。著者の伊藤益(すすむ)氏は親鸞研究者。私の大学時代からの親友だ。
彼はこれまで、多くの書物を著してきたが近年は文体が変わった。いわゆる「学者様」を「降りた」伊藤君は、実に読みやすい文章を書く。書物の内容は、かなり専門的であるのだが、文体に読者への配慮がある。
以下に、本書の感想を記す。かなり長いので、仏教や浄土真宗、浄土宗に余り関心のない方は、ここで読了として頂きたい。
「やさしさ」とは何か~伊藤益『私釈法然』を読んで~
旧盆に、親友にして畏友の筑波大学教授伊藤益氏の新著『私釈法然』(2016年、北樹出版)を読んだ。氏はこれを、多分、一気に書き上げたに違いない。著者の命題である「法然から親鸞へ」への解答がここに記された。「これを書かずに死ぬ訳にはいかぬ」という鬼気迫る著者の想いが伝わってくる。
とは言え、本書は、過激な文体では全く綴られていない。「です、ます」調の敬体で、至極やさしく穏やかな語り口で全体が綴られている。この語り口こそが、法然をして、「一言でいえば「やさしい人」であった…浄土宗の隆昌は、開祖のその「やさしさ」によって支えられていたように思われます」(34頁)との著者の言に繋がる。ギリギリまで突き詰め、自らの中での死闘のうちにようやく得た「命題への解答」を、やさしい語り口で語るという行為の根底には、著者の「読者への深い眼差し」が存在する。
「法然は、学問すること自体を否定したわけではありません。学問をしてことの細部に拘泥するあまり、「弥陀助けたまえ」という単純きわまりない願望がいずこへともなく消え去ることを、彼は危惧したのです。…法然の浄土宗とは、余分な学知や不必要な教理を徹底的にそぎ落としたもの、いわば、極限まで切り詰められた教えでした」(78頁)と語ることで、著者は「学問の根本態度」を示唆する。「真理を追求する学問とは如何にあるべきか」という命題への明快な解答がここにあろう。そして、著者もまた、そのような態度で学問を積む人物である。
しかし、法然は、自らの真理を追求することだけで満足するような人物ではなかった。「法然は己れ自身に向かうときの顔と、弟子たちに向き合うときの顔とが異なる宗教者でした。…自己自身に対する極度の厳しさが、弟子や門徒たちに対する慈愛に満ちた温顔に転化するところに、法然の特徴はあった、といっても間違いではないでしょう」(93頁)と著者は語る。自らへの極度の厳しさに加えて、「他者へのやさしさ」こそが、法然を一流の宗教家たらしめている。この辺りを読んで、「他力本願とは、自力の否定とともに、他者への大いなる配慮からこそ成り立っているのではなかろうか」と感じた。
このような新たな法然像を明らかにしながら、終章で、「法然から親鸞へ」という著者の命題への解答が語られている。まず、「わたしは、親鸞が法然を超えているとは考えません。…弟子は、師が気づきながらもどうしても説きえなかったことを、自身の問題となしうるだけの環境に恵まれていた。わたしは、法然と親鸞との関係をそのように理解したいと思っています」(198頁)と、師弟の関係性が明確に語られる。そして、「民衆に眼差しを向けることの重要性を親鸞が知ったのは、法然の教えを受けたがゆえだという点です。…かりにもし親鸞が法然という師をもたなかったとすれば、親鸞の思想は己れの内面をえぐり出すことにのみ終始することになったのではないでしょうか。法然は、「超越」の高みにのぼってしまおうとする自己を必死にくいとめながら、一切衆生の救済ということを説きつづけた思想家でした」(207頁)と続く。この言は極めて重要だ。「真理を究め高みに登り切ろうとする己自身を厳しく諫め、一切の衆生の救済を第一義に考えるべし」との法然の姿勢が弟子の親鸞を高めた。この師なくしてこの弟子なしである。その意味で、法然は親鸞思想の根底にある人物となる。「法然なくして親鸞なし」との感を得た。
このような法然像を私たちに伝えてくれた著者に深く深く感謝したい。「やさしさ」とは何かーそれは正に、命がけの他者への配慮であり、眼差しではなかろうか。それを私たちに知らしめてくれた著者もまた、法然の如き「やさしい人」なのである。
感想は、以上。ここまで読んで頂いた方々に感謝したい。もしもよろしければ、ご自分で1冊ご購入されるか、学校図書館などにお入れ頂きたい。価格は、「2000円+税」。よろしくお願いします。