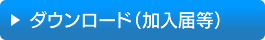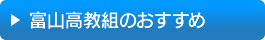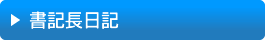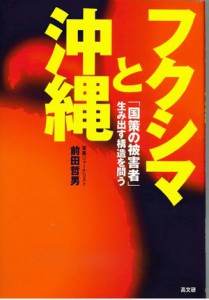 「この小さな本に書いていくのは、いわゆる「フクシマ論」ではない。(中略)日本人の核意識を、「原発とフクシマ」および「軍事基地とオキナワ」という、ひとつの枠組みのなかで考えていくことである。(中略)「フクシマと沖縄」はおなじ次元の問題として把握できる、いや、そう把握すべきだ、と考えるようになった」(1頁)。この本書冒頭にある文章が、筆者の立ち位置を明確に表している。
「この小さな本に書いていくのは、いわゆる「フクシマ論」ではない。(中略)日本人の核意識を、「原発とフクシマ」および「軍事基地とオキナワ」という、ひとつの枠組みのなかで考えていくことである。(中略)「フクシマと沖縄」はおなじ次元の問題として把握できる、いや、そう把握すべきだ、と考えるようになった」(1頁)。この本書冒頭にある文章が、筆者の立ち位置を明確に表している。
1938年生まれの筆者は、現在は軍事ジャーナリストとして高名だが、若き日は長崎放送に勤務し、佐世保で原潜寄港反対闘争を取材した。その後、フリーになり、最初に沖縄での米軍毒ガス撤去を取材した。これらの経験が本書成立の基盤となっている。
さて、筆者はフクシマと沖縄の共通性を次のように述べる。「第一は、(中略)どちらもオキナワ、フクシマと、片仮名の「普通名詞」であらわされる点にある。米軍基地オキナワ、原発地帯フクシマは、ヒロシマとナガサキとともに、普遍的な日本の地名になった」(87頁)。「第二に、沖縄と福島が、ともに“まつろわぬ者”たちの末裔、また“寄る辺なき民”としてのルサンチマン(怨念)と哀切な記憶を共有している点であろう」(88頁)。「第三の共通点は、ともに「国策の生贄(いけにえ)」となった戦後の歩みにおいてである。フクシマのシンボルが「原子炉と温排水」であったとすれば、オキナワの戦後は、「星条旗と基地のフェンス」に象徴されよう」(91~92頁)。
これらをまとめると、両者の共通性とは「ともに、辺境の民が国策の生贄となり、それが世界的にも有名になった点」だと言えよう。しかし筆者は言う、「まだ大多数の人は、「フクシマとオキナワ」を、いまだひとつのつながりとして受け止めていない」(103頁)と。私たちは、このような「犠牲の構造」を直視し、世直しのための行動をとらねばならない。
〈評・高木 哲也〉
高文研、2012年、1600+税 (14年12月10日)