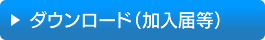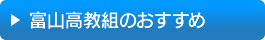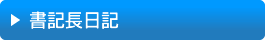プラトン以来、「徳は教えられるのか?」が問い続けられ、「道徳教育」の困難性が語られてきた。しかし文科省は2018年度から「道徳」を教科化しようとしている。当然ながら多くの識者から批判が湧き起こった。
プラトン以来、「徳は教えられるのか?」が問い続けられ、「道徳教育」の困難性が語られてきた。しかし文科省は2018年度から「道徳」を教科化しようとしている。当然ながら多くの識者から批判が湧き起こった。
本書は、10年以上前に出版されたものだが、現在も大いに参考になる。編者の土戸以下17名の執筆陣は全て大学人だが、文章は比較的平易である。以下に、特徴的な記述を3点紹介したい。
1958年に特設された「道徳の時間」に関して、新谷恭明は、「特設に際して日本教育学会は、「個人の自由と良心の問題である道徳とその授業について、公権力が一定の方向づけやわくづけをすることが、はたして妥当であるかどうかが考えられなければならない」として批判した。人間の良心の問題に公権力が干渉することについての危惧がこのときの議論の背景にあったのである」(92頁)と紹介する。現在の「道徳の教科化」にも同様に当てはまる危惧だ。
土戸敏彦は、「道徳とは、その社会を構成しているいわば正規の成員、つまり大人たちが設定したものだ」(10頁)と指摘する。現在、安倍「教育再生」が推し進める道徳もまた、社会の「(最高に)正規の成員」である政権担当者が設定したものだ。
さらに土戸は、「道徳的行為の“美しさ”は、作為性のないところで現れるように思われる。(中略)「道徳的でござい」というこれ見よがしのわざとらしい行為が、少しも胸を打たないどころか、嫌悪感さえ催させるのは必然なのである。そういう意味で〈道徳〉の授業は、まさに危うい位置にあるわけだ」(15~16頁)と述べる。現在の「押しつけ道徳」にピタリと当てはまる嫌悪感だ。
「教えること」の可能性自体に疑問がある「道徳」を一気に教科にするー本書は、この馬鹿馬鹿しさを実感させてくれる書である。
〈評・高木 哲也〉
教育開発研究所、2003年、2000円+税 (14年12月25日)