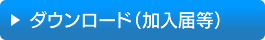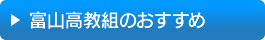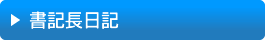いま、部活動問題が大きくクローズアップされる中で実にタイムリーに出版された本。特に戦後の部活の歴史の記述が有益だ。本書は、「(戦後、部活がこれほど拡大した背景に)3つの時代とキーワードがあった。1つめは、戦後改革の時代の民主主義。2つめは、東京オリンピックの時代の平等主義。3つめは、校内暴力の時代の管理主義。部活は、学校全体のあり方や社会の状況と関連していて、その関連が積み重なって、ここまで拡大してきた」(77頁)と述べる。
いま、部活動問題が大きくクローズアップされる中で実にタイムリーに出版された本。特に戦後の部活の歴史の記述が有益だ。本書は、「(戦後、部活がこれほど拡大した背景に)3つの時代とキーワードがあった。1つめは、戦後改革の時代の民主主義。2つめは、東京オリンピックの時代の平等主義。3つめは、校内暴力の時代の管理主義。部活は、学校全体のあり方や社会の状況と関連していて、その関連が積み重なって、ここまで拡大してきた」(77頁)と述べる。
戦後、部活動の性格は、「生徒の自主的、自発的な参加により行われるもの」と規定され、「部活の中心には、生徒の「自主性」がある」(50頁)として戦後の民主主義と連動して発展した。これが「1つめ」。
「2つめ」は、東京オリンピックによるスポーツ熱の盛り上がりによって、スポーツの機会を平等に保障しようとする機運が部活を動かしたこと。これを象徴する政策が「必修クラブ活動」である。これには当時の日教組が、「必修は自主性に背く」として猛反発した。
最後の「3つめ」は、1980年代の学校で発生した校内暴力と生徒の非行化への対応としての部活である。「非行防止手段として部活が意味づけられたこと」に対し本書は、「皮肉にも、管理主義がその「自主性」を利用することで、部活はかつてないほど大規模に拡大していった」(77頁)と述べる。
その後、現在は、「大規模に拡大した部活は、もはや学校や教師のみで支えることが難しくなった。部活は、学校と教師を苦しめる、排除されるべき教育問題として扱われるようになった」(77頁)と本書は捉えている。このような状況に対して、「部活のあり方は、あくまで法律の中で、道徳の中で考えられなければならない」(229~230頁)との本書最終部分での著者の提言には考えさせられた。部活の歴史とあり方を学ぶ好著である。
〈評・高木 哲也〉 大月書店・2017年・1800円+税 (17年4月18日)